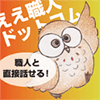築40年以上の家は要注意!旧耐震基準の屋根構造が抱えるリスクとは
2025/08/21
現在お住まいの住宅が、どの年代の耐震基準に基づいて建築されたものかご存知でしょうか。耐震基準には旧耐震基準と新耐震基準があり、揺れに対する住宅の強度が大きく異なります。特に、築40年以上経過している住宅は注意が必要です。この記事では、耐震基準の移り変わりや旧耐震基準の屋根構造が抱えるリスクなどを詳しく解説します。築40年以上の住宅にお住まいの方や耐震基準について詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
旧耐震基準と新耐震基準
耐震基準とは、地震の揺れに対して建物が最低限の耐震能力を持つことを保証し、建築を許可する基準です。1950年の建築基準法施行令によって規定された耐震基準(旧耐震基準)は、震度5程度の揺れに対して建物が耐えることを目標にしていました。大きな地震に見舞われる度に基準が引き上げられ、1981年6月1日に導入された新耐震基準では、震度5強程度の揺れに対してほとんど損傷が生じず、震度6強~震度7程度の地震に対して人命を脅かすような倒壊等の被害が生じないことが目安となりました。2000年6月には、木造建築において地盤調査の事実上義務化や筋交い接続部への金物の取り付け、耐力壁のバランスを考慮した配置など、新耐震基準がより強化されています。そのため、築40年以上の住宅で旧耐震基準を元に建築されたものに関しては、建物の耐震能力が現代の基準に比べて低く、強い揺れを受けた際に倒壊などのリスクが懸念されています。
耐震基準の判別方法

現在お住まいの住宅が旧耐震基準か新耐震基準かを判別するには、建築確認申請の日付を確認することがおすすめです。1981年6月1日以降に建築確認申請が提出された建物は新耐震基準ですが、それ以前は旧耐震基準となります。ただし注意が必要なのは、建築確認申請から実際の完成まで1~2年かかることも多いため、1983年以前に建てられた建物は旧耐震基準の可能性もあるということです。建築確認通知書や検査済証で正確な日付を確認しましょう。
旧耐震基準の屋根が抱える2つのリスク
旧耐震基準の屋根が抱えるリスクは、大きく分けて「重い屋根材」と「構造的な弱さ」の2つがあります。
重い屋根材が引き起こす危険性
旧耐震基準の建物では、日本の風土に合った伝統的な屋根材として、重い粘土瓦が広く使われていました。この瓦屋根の重さは、1平方メートルあたり約50~60kgにもなります。一般的な30坪程度の住宅の屋根全体では、約6トンもの重量となり、これは軽自動車6台分に匹敵する重さです。この「重さ」こそが、旧耐震基準の屋根が抱える最大のリスクの一つです。地震が発生した際、建物の揺れは屋根の重量によってさらに大きくなります。いわゆる「重心が高くなる」ことで、揺れが増幅され、家全体が受ける負荷が急激に高まってしまうのです。これは、重いものを頭に乗せた状態で激しく揺さぶられるようなもので、家全体にかかる負担が大きくなり、最悪の場合、柱や壁が耐えきれずに倒壊するリスクを高めてしまいます。一方、新耐震基準以降に建てられた家では、このリスクを軽減するために軽量な屋根材が普及しました。特にガルバリウム鋼板などの金属屋根は、瓦屋根の約10分の1以下の重さであり、地震時の揺れを大幅に抑える効果があります。屋根の軽量化は、建物の耐震性を向上させる上で非常に効果的な対策なのです。
構造材の劣化と接合部の弱さ
屋根の重さだけでなく、内部の構造的な問題も無視できません。築40年以上の家では、屋根を支える木材(垂木、野地板など)が長年の雨風や湿気により徐々に劣化しています。特に、雨漏りが発生していたり、換気が不十分な屋根裏では、木材の腐食が進行している可能性が高いです。腐った木材は強度を失い、地震の揺れに耐えることができません。また、旧耐震基準の建物では、構造材の接合方法にも問題がある場合があります。当時は釘やボルトのみで接合されているケースが多く、地震の強い横揺れが加わると、接合部が外れたり、木材が割れたりするリスクが高まります。これにより、屋根全体が建物から脱落する危険性も否定できません。新耐震基準では、地震の揺れによる部材の脱落を防ぐため、構造材の接合部に「金物」で補強することが義務付けられています。金物補強が施された屋根構造は、地震のエネルギーを効果的に分散・吸収し、建物の安全性を大幅に向上させます。屋根の内部まで専門家が診断することで、こうした目に見えない構造的な弱点を発見できるのです。
実際の地震で明らかになった住宅被害の明暗
1995年の阪神・淡路大震災では、古い木造住宅の倒壊が大きな被害をもたらしました。特に神戸市の長田区などでは、築年数の古い住宅が密集していたこともあり、多くの家屋が倒壊。その多くに共通していたのが「重い瓦屋根」と「旧耐震基準の構造」でした。また、2016年の熊本地震では、新耐震基準の住宅でも屋根が重い家は損壊が大きい傾向にあったとの調査結果も出ています。屋根を軽くしていた住宅は、同程度の揺れでも損傷が軽微にとどまることが多かったのです。実際、耐震補強や屋根の軽量化を事前に行っていた住宅は、倒壊を免れたという事例も多く報告されています。このように、実際に発生した地震による被害でも、「屋根の重さ」と「耐震基準」が住宅被害の明暗を分けたことがわかっています。
耐震面に影響する屋根のセルフチェックポイント

自宅の屋根が耐震面において危険な状態かどうか、まずは次のようなポイントをチェックしてみましょう。
✅屋根材は何か?
重い瓦が使われていないか。特に築40年以上で瓦が載っている場合は要注意。
✅屋根がたわんでいないか?
中心部が沈んでいたり、歪んで見える場合は構造材の劣化の可能性あり。
✅雨漏りの跡がないか?
天井にシミやカビがある場合は、屋根や構造材の腐食が進んでいる可能性あり。
✅天井裏(小屋裏)の状況
木材がボロボロになっていたり、接合部が緩んでいたら注意。
✅建築年と耐震診断の有無
1981年6月1日以前に建てられた家で、耐震診断を受けたことがないなら早急に相談を。
一つでも心当たりがある場合は、専門家に相談することをおすすめします。
自分でできる屋根の劣化状態チェック

耐震面におけるチェックが終わったら、次に屋根の劣化状態を確認してみましょう。屋根の劣化は耐震面に影響しにくいものがほとんどですが、長期的な目で見ると雨漏りなどで構造部に影響を及ぼす場合もあります。地上から双眼鏡などを使って、以下のポイントをチェックしてみてください。
✅屋根材のズレや割れ
瓦やスレートにひび割れや欠けがないか、瓦がずれて隙間ができていないかを確認します。少しのズレやひび割れでも、そこから雨水が侵入し、内部の構造材を腐食させる原因になります。
✅雨樋の損傷
雨樋が歪んで水が正常に流れなくなっていないか、外れていないかをチェックします。雨樋が機能しないと、屋根から落ちた水が壁や基礎に直接あたり、建物の劣化を早めます。
✅棟瓦の漆喰の劣化
瓦屋根の頂上にある棟瓦を固定している漆喰に注目します。漆喰が剥がれていたり、ひび割れが目立つ場合は、棟瓦がズレやすくなっているサインです。
これらのセルフチェックで異常が見つかった場合はすぐに専門家へ相談し、屋根の劣化を修復しましょう。
耐震性を向上させるための具体的なリフォーム・対策案

耐震性を向上させるためには、「屋根の軽量化」や「耐震補強・構造材の補修」が効果的です。
屋根の軽量化リフォーム
旧耐震基準の屋根が抱えるリスクを根本的に解決するためには、リフォームが最も有効な手段です。屋根を軽量化するリフォームには、主に「葺き替え」と「カバー工法」の2種類があります。
葺き替え
既存の屋根材をすべて撤去し、野地板や防水シートも新しくしてから新しい屋根材を葺く方法です。屋根材を撤去するため、内部の構造材の状態を直接確認・補修できるメリットがあります。費用はかかりますが、最も確実な対策です。
カバー工法
既存の屋根材の上から、新しい軽量な屋根材を被せる方法です。瓦屋根には適用できませんが、スレート屋根などには有効です。既存の屋根を撤去しないため、工期が短く、費用も比較的安く済むメリットがあります。
軽量な屋根材としては、ガルバリウム鋼板などの金属屋根がおすすめです。軽量であることに加え、耐久性やデザイン性にも優れています。また、自治体によっては、耐震改修やそれに伴う屋根のリフォームに対して補助金制度を設けている場合があります。活用できる制度がないか、事前に調べてみましょう。
耐震補強と構造材の補修
屋根のリフォームと合わせて、家全体の耐震性を高めることも重要です。まずは専門家による耐震診断を受け、家全体のリスクを把握した上で、適切な補強計画を立てることをお勧めします。屋根の構造自体を補強する対策としては、屋根を支える木材の接合部に専用の金物を取り付ける方法があります。これにより、地震時の揺れに対する強度を高めることができます。また、雨漏りが発生している場合は、劣化した防水シートを交換したり、腐食した木材を新しいものに取り替えたりする補修も必須です。これらの対策は、建物の寿命を延ばし、安全性を長期的に確保するためにも欠かせません。
まとめ
この記事では、耐震基準の移り変わりや旧耐震基準の屋根構造が抱えるリスクなどを詳しく解説しました。まずは、お住まいの住宅の耐震性を正しく理解し、足りない部分はリフォームによる改修工事などで補うことが大切です。
Re,ルーフは京都市を中心に京都全域に対応可能です。築40年以上の耐震診断を受けたことがない住宅にお住まいの方は、早めの診断がおすすめです。屋根裏などの構造部も点検可能ですのでお気軽にご連絡ください。
〈葺き替え工事の施工例はコチラ〉