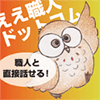「瓦の耐震性は弱い」は誤解?現代瓦の耐久性と耐震性能を徹底解説
2025/11/12
瓦だと耐震性が低いと言われることがありますが、地震で建物が倒壊する本当の原因は瓦ではありません。耐震性を高めるには、屋根の軽量化を含めた耐震補強工事を行う必要があります。
現在では、従来の瓦よりも軽量化された「軽量防災瓦」も登場しており、地震にも強い屋根を作ることができます。
この記事では、瓦のままで災害に強い屋根にするためのポイントを解説します。
瓦=耐震性が低いは誤解?

瓦屋根だと耐震性が低いから避けたほうが良いと言われることがあります。
確かに屋根が重ければ、地震の際に屋根の重みが柱や壁の負担になり、倒壊につながってしまうことがあります。
しかし、瓦屋根だから必ず倒壊するわけではありません。
地震によって建物が倒壊する原因は、様々で瓦屋根の重さはその原因の一部に過ぎません。
地震で建物が倒壊する本当の原因とは?
地震で建物が倒壊するのは、屋根が重いからではありません。
地震で建物が倒壊する原因は大きく2つあります。
✔地盤が弱く建物が揺れやすい
✔建物が地震に耐えられる構造になっていない
一つ一つ確認しましょう。
地盤が弱く建物が揺れやすい
地盤が緩い場所に建物を建てた場合は、地震の際に建物の揺れが増幅されます。
その分、建物の負担が大きくなり、倒壊しやすくなるということです。
そのため、建物を建てる際は、その土地の成り立ちに注目することが非常に大切です。特に埋立地や盛り土した土地の場合は、地盤が弱い可能性があります。
昔は田んぼだった土地や水路が流れていた地域も、地盤が弱いので注意が必要です。
建物が地震に耐えられる構造になっていない
建物の構造が地震に耐えられる強度を有していないことも地震で建物が倒壊する大きな原因の一つです。
戸建て住宅の耐震性基準については、大地震を経験するごとに年々強化されてきました。
1981年に新耐震基準が設けられ、震度6強程度の地震でも倒壊しない耐震性が求められるようになりました。
その後、1995年の阪神淡路大震災を受けて、震度7クラスでも倒壊しない2000年基準という耐震性が制定されています。
現在では、耐震基準とは別に「耐震等級」というランクが設けられており、2000年基準で建てられた建物が「耐震等級1」とされています。
耐震等級1で想定している地震の1.25倍の地震に耐えられる場合は「耐震等級2」、1.5倍の地震に耐えられる場合は「耐震等級3」になります。
そのため、2000年基準で建てられているかどうかが、地震に耐えられる構造になっているかどうかを判断する一つの目安になります。
2000年以前に建てた家の場合、耐震補強しないと、耐震性が十分ではない可能性があるわけです。
地震に耐えられる構造にするには?
現在建っている建物を地震に耐えられる構造にする工事のことを耐震補強工事といいます。
耐震補強工事として主に行われる工事が、次の4つです。
壁の増設:構造用合板などで壁を作ったり、壁内部に筋交いを入れる工事
基礎の補修と強化:基礎を打ち増ししたり、ひび割れを補強する工事
金具補強:柱や梁、土台を金具で止めて強固に緊結する工事
屋根の軽量化:重い屋根を軽量な屋根に変える工事
この4種類の工事はバランスよく行うことが大切です。どれか一つだけ施工しても、大した耐震性向上にはつながりませんし、むしろ、建物のバランスが悪くなって倒壊しやすくなることもあります。
特に、瓦屋根から軽量な屋根に変えただけで、耐震性が大きく向上することはないということに注意が必要です。
大地震時の瓦屋根の被害とは?

大地震の際に、瓦屋根が建物にもたらす被害は大きく二つ挙げられます。
一つは、瓦の重さが建物の負担になって倒壊のリスクが高まること。
もう一つは、瓦がズレたり、屋根から崩れ落ちる形で屋根が壊れてしまう被害です。
昔の瓦は、釘などで屋根に留められているわけではなく、屋根に積み重ねられているだけです。
そのため、地震の揺れによって崩れ落ちることがありますし、台風が直撃すると風で飛ばされたりズレてしまうこともあります。
そこで、2019年の令和元年房総半島台風をきっかけに、瓦を固定することが義務付けられました。
このガイドライン工法と呼ばれる施工方法を採用している場合、地震により瓦が崩れ落ちるリスクは少なくなります。
現代では、「軽量防災瓦」と呼ばれるタイプの瓦も登場しており、従来の瓦に比べて地震に強い瓦屋根にすることも可能です。
現代の新しい軽量防災瓦とは?
瓦は伝統的な屋根材で、化粧スレートや金属屋根といった新しい屋根材が登場する中で時代遅れになっているイメージがあるかもしれません。
しかし、瓦も時代の要請に応じて進化しています。
今では、軽量瓦、防災瓦、この二つの性質を併せ持った軽量防災瓦といった瓦が登場しています。
✅軽量瓦とは?
軽量瓦とは、従来の瓦よりも軽量化された瓦のことです。
従来の瓦は、1㎡あたり50kg程度の重量があります。この重量を10%〜30%程度軽量化し、1㎡あたり35kg程度まで軽量化した瓦のことを軽量瓦と言います。
軽量瓦は基本的にガイドライン工法に則って施工されるため、地震の際に崩れたり、台風の際にズレたり飛ばされるリスクの低い瓦になります。
✅防災瓦とは?
防災瓦とは、地震や台風が直撃した際にズレたり崩れたりしにくい瓦のことです。
瓦同士を引っ掛けるアームと呼ばれる部分があり、釘なしでもズレにくい構造になっています。
ガイドライン工法に則って施工すれば、地震や台風の被害を大幅に防ぐことができます。
✅軽量防災瓦とは?
軽量防災瓦とは、軽量であり、かつ、瓦同士を引っ掛けるアームの部分があるため、防災瓦としての機能も有している瓦のことです。
軽量瓦、防災瓦と呼んでいる場合でも、軽量防災瓦のことを指していることも多いです。
軽量防災瓦は、従来の瓦に比べると建物への負担が少ない上、地震や台風の被害にも強いです。
更に瓦としての耐久性も併せ持っているので、他の屋根材よりも耐用年数が長くなります。
軽量防災瓦のメリット

普通の瓦や他の屋根材と比較した場合の軽量防災瓦のメリットは次のとおりです。
✔地震や台風に強い
✔意匠性が高い
✔遮音性が高い
✔断熱性に優れている
✔防水性に優れている
✔耐久性が高い
✔メンテナンスしやすい
一つ一つ確認しましょう。
地震や台風に強い
普通の瓦と比較した場合のメリットとして、地震や台風に強い事が挙げられます。
普通の瓦よりも軽量なので、建物にかかる負担が軽減されますし、普通の瓦よりも強固に緊結されるため、地震の揺れや台風の強風にも強くなります。
意匠性が高い
軽量防災瓦を施工した際の雰囲気は、普通の陶器瓦と大差ありません。
そのため、化粧スレートや金属屋根よりも重厚な屋根を作ることができます。
遮音性が高い
軽量防災瓦は瓦の一種なので、普通の瓦と同様に遮音性が優れています。
激しい雨が降った際など、特に金属屋根だと雨音が気になってしまうことがありますが、軽量防災瓦ならそのような心配はありません。
断熱性に優れている
瓦は、化粧スレートや金属屋根よりも断熱性に優れていますが、軽量防災瓦も同様に断熱性に優れています。
防水性に優れている
瓦は、一枚一枚葺くため、隙間が生じやすく防水性で劣る面があります。
その点、軽量防災瓦は、瓦同士がズレにくく、雨水が入りにくいように計算して設計されています。そのため、瓦と比べると防水性の面でも優れています。
耐久性が高い
軽量防災瓦は、通常の瓦と同様の耐久性があります。
そのため、化粧スレートや金属屋根と比べると耐用年数が長くなります。
メンテナンスしやすい
化粧スレートや金属屋根は、屋根材の劣化を抑えるために塗装が必要です。
軽量防災瓦は、瓦でできているため、塗装する必要がありません。
その分、メンテナンスの頻度を減らすことができ、コストパフォーマンスが良いと言えます。
軽量防災瓦のデメリット

普通の瓦や他の屋根材と比較すると、軽量防災瓦にはデメリットもあります。
✔重い屋根材であることに変わりはない
✔初期費用が高い
✔割れる可能性はある
一つ一つ確認しましょう。
重い屋根材であることに変わりはない
軽量防災瓦は、軽量であることが売りですが、これは普通の瓦と比較した場合の話です。
化粧スレートや金属屋根と比べると重い屋根材であることに変わりはありません。
屋根の軽量化を重視して選ぶなら、金属屋根が最善の選択肢になります。
初期費用が高い
瓦は他の屋根材と比べても初期費用が高めになります。軽量防災瓦も瓦の一種なので、化粧スレートや金属屋根と比べると初期費用が高くなります。
割れる可能性はある
軽量防災瓦は、防災瓦とあるだけに、地震や台風の際のあらゆる被害を防げるイメージがあるかもしれませんが、瓦であることに変わりはありません。
そのため、屋根に物がぶつかった場合は、割れてしまうリスクがあります。
まとめ
この記事では、地震に強い家にするためには、屋根の軽量化を含めた耐震補強工事が重要であることと、瓦のままでも地震に強い家にすることができることを解説しました。
軽量防災瓦は、瓦の意匠性を残したまま、従来よりも、災害に強い屋根にすることができます。
Re,ルーフは、京都市右京区を中心に活躍する屋根工事職人直営店です。京都市や亀岡市などを中心に京都府全域で屋根工事や雨漏り修理工事を承っています。
屋根を軽量化したり、軽量防災瓦を施工するといった工事にも対応しております。
災害に強い屋根にしたいとお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。