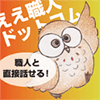安さで選ぶと危険?屋根材ごとの“盲点”と失敗しない屋根材の選び方
2025/05/26
屋根の葺き替えやカバーリングのリフォームにおいて、屋根材選びは非常に重要です。価格だけで選んでしまうと後々後悔する可能性もあるため、慎重に選ぶ必要があります。
この記事では、住宅の屋根リフォームで後悔しないよう、ご自宅の状況や予算に合わせた最適な屋根材の選び方を解説します。各種屋根材の特徴やメリット・デメリット、注意点などを知ることで屋根材に関する知識が深まり、安心してリフォーム計画を進めることができるでしょう。
なぜ屋根材選びが重要?

屋根は夏の強烈な日差しや冬の厳しい寒さなど、過酷な条件下から生活空間を守っています。屋根材は住まいの快適性や安全性、そして美観を支える極めて重要な部分です。だからこそ、新築時はもちろん、リフォーム時の屋根材を慎重に選ぶ必要があるのです。
価格だけで選ぶことの危険性
屋根リフォームを検討する際、多くの方がまず気になるのが「費用」でしょう。複数の業者から見積もりを取り、できるだけ安く抑えたいと考えるのは自然なことです。
しかし、初期費用(イニシャルコスト)の安さだけで屋根材を選んでしまうと、将来的に大きな後悔を招く可能性があります。例えば、次のような事例です。
数年で色あせやひび割れが発生し、美観が損なわれる。
10年も経たないうちに再塗装や部分修理が必要になる
維持費用(ランニングコスト)が高くつく
夏は暑く冬は寒く、雨音がうるさい
屋根材選びで考慮すべき5つの基本ポイント

では、具体的にどのような点に注意して屋根材を選べば良いのでしょうか。ここでは、後悔しないための基本的な5つのポイントをご紹介します。
屋根材選びのポイント①✅耐久性・耐用年数
屋根材にはそれぞれ想定される耐用年数があります。日本の気候は四季の変化が大きく、梅雨や台風、地域によっては積雪など、屋根にとっては過酷な環境です。これらの条件下で、どれだけ長期間性能を維持できるかを確認しましょう。
一般的に、瓦は非常に耐久性が高く、金属屋根も適切にメンテナンスすれば長持ちします。スレートやアスファルトシングルは、これらに比べると耐用年数が短い傾向にあります。
屋根材選びのポイント②✅メンテナンス性
メンテナンスの頻度や内容は屋根材によって大きく異なります。例えば、スレート屋根は10〜15年ごとの塗装が推奨されますが、日本瓦は瓦自体の塗装は不要です。
メンテナンスには当然費用も発生しますので、その頻度と1回あたりのコスト、そして足場代なども考慮に入れる必要があります。
屋根材選びのポイント③✅初期費用とライフサイクルコストのバランス
初期費用は重要な比較ポイントですが、それだけで判断するのは早計です。前述のメンテナンス費用に加え、耐用年数も考慮した「ライフサイクルコスト」で比較検討することが賢明です。
初期費用が高くても、耐用年数が長くメンテナンス頻度が少なければ、長期的にはお得になるケースもあります。逆に、初期費用が安くても、頻繁なメンテナンスや早期の葺き替えが必要になれば、トータルコストは高くなります。
屋根材選びのポイント④✅デザイン性・美観
屋根は住まいの外観イメージを大きく左右します。色、形状、素材感など、建物のスタイル(和風、洋風、モダンなど)や外壁の色、さらには周囲の景観との調和も考慮して選びましょう。
屋根材によってはカラーバリエーションが豊富なものや、特定のデザインにしか合わないものもあります。長く愛せるデザインを選ぶことも大切です。
屋根材選びのポイント⑤✅機能性
住まいの快適性や安全性に関わる機能も屋根材選びの重要な要素です。
✔断熱性・遮熱性
冷暖房の効率を左右し、光熱費に影響します。特に夏場の室温上昇を抑える遮熱性能は重要です。
✔遮音性
雨音などの騒音を軽減できます。
✔軽量性
地震時の揺れが小さくなるため耐震性が向上します。特に古い木造住宅のリフォームでは重視すべき点です。
✔防火性
隣家からの火災の燃え移りや、自宅からの火災の広がりを防ぐ上で重要な性能であり、特に都市部では欠かせません。
【種類別】代表的な屋根材のメリット・デメリットと費用相場

日本の住宅でよく使用されている代表的な屋根材について、それぞれの特徴(メリット・デメリット)、耐用年数やメンテナンス方法、費用相場、そして見落としがちな盲点を詳しく解説していきます。
【比較表】主要屋根材の特徴・費用・メンテナンス一覧
| 屋根材 | 耐久性 | 初期費用
(㎡単価) |
重量
(kg/㎡) |
メンテナンス | 断熱性 | 遮音性 |
| スレート | 20~30年 | 4,000~7,000円 | 約20 | 10~20年毎塗装 | △ | △ |
| ガルバリウム鋼板 | 25~40年以上 | 6,000~10,000円 | 約5 | 20~30年毎塗装 | △ | × |
| 粘土瓦 | 50年以上 | 9,000~18,000円 | 約40~60 | ほぼ不要 | 〇 | ◎ |
| アスファルトシングル | 15~30年 | 5,000~9,000円 | 約10~13 | 部分補修 | △ | △ |
| セメント瓦 | 20~30年 | 4,000~7,000円 | 約40~50 | 10~20年毎塗装 | 〇 | 〇 |
※上記費用はあくまで一般的な目安であり、使用する材料のグレード、施工面積、地域などによって大きく変動します。
スレート屋根(カラーベスト・コロニアル)

スレート屋根は、セメントを主成分として繊維素材で補強して作られる薄い板状の屋根材です。「カラーベスト」や「コロニアル」といった商品名でも知られ、新築の戸建て住宅で広く採用されています。
メリット
スレート屋根のメリットは、初期費用が比較的安く、軽量で耐震性に優れている点です。また、色のバリエーションが豊富で、施工がしやすいという利点もあります。
デメリット
スレート屋根は薄い板状のため、割れやすく、定期的な塗装メンテナンスが必須です。また、経年劣化により色褪せや汚れが目立ち、美観が損なわれやすいというデメリットがあります。
耐用年数の目安とメンテナンス方法
スレート屋根の耐用年数は約20〜30年ですが、これは定期的な塗装などのメンテナンスを行った場合の目安です。メンテナンスとしては、10〜20年ごとの塗装による防水性の維持と棟板金の点検・交換が必要です。
注意点
スレート屋根の塗装後には、塗料が重なり部分に固着して水の抜け道を塞ぐことがあるため、縁切り作業が不可欠です。この作業を怠ると雨漏りの原因になります。
また、2004年以前の製品にはアスベストが含まれている可能性があり、撤去・処分には特別な処理と高額な費用が必要となるため、リフォーム前に専門業者に調査を依頼することが重要です。
ガルバリウム鋼板(金属屋根)

ガルバリウム鋼板は、アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板のことで、近年非常に人気が高まっている金属屋根材です。耐久性、軽量性、デザイン性に優れ、新築はもちろんリフォームにも適しています。
メリット
ガルバリウム鋼板は耐久性が高く、錆びにくく長期間美しい状態を保てます。また、軽量で耐震性に優れ、スタイリッシュなデザインと豊富なバリエーションが可能です。カバー工法にも適しており、緩勾配の屋根にも対応できます。
デメリット
ガルバリウム鋼板は初期費用がスレート屋根よりやや高く、雨音が響きやすく、衝撃で凹みやすい性質があります。また、熱伝導率が高いため、夏場は表面温度が高温になります。
耐用年数の目安とメンテナンス方法
ガルバリウム鋼板の耐用年数は約25〜40年以上とされていますが、SGL鋼板などの高耐久製品ではさらに長くなることもあります。ただし、沿岸部など塩害の影響を受けやすい地域では耐用年数が短くなる場合があるため、高耐食性の製品を選ぶと良いでしょう。
基本的なメンテナンスは少なく済みますが、定期点検で飛来物による傷や凹み、固定金具の緩みなどを確認することが推奨されます。20〜30年程度で再塗装を検討しますが、塗膜の保証内容を確認することが重要です。
注意点
ガルバリウム鋼板は断熱性や遮音性が低いため、快適な住環境には断熱材一体型製品を選ぶか、別途断熱材や遮音シートの施工が必要です。
また、遮熱塗料を塗布することで、夏場の室温上昇を抑え、エアコン効率を上げることができます。これらの対策費用も考慮しましょう。
粘土瓦

粘土瓦は、粘土を成形し高温で焼き上げた伝統的な屋根材です。その歴史は古く、日本の気候風土に適した優れた性能を持っています。
大きく分けて、表面に釉薬(ゆうやく)を塗って焼き上げる「釉薬瓦(陶器瓦)」と、釉薬を塗らずにいぶして炭素膜を形成させる「いぶし瓦」があります。
メリット
粘土瓦は断熱性、遮音性、通気性に優れるうえに耐久性が非常に高く、50年以上、中には100年以上持つものもあり長寿命です。紫外線や雨風による劣化もほとんどありません。
また、塗装メンテナンスは基本的に不要で、部分的な交換も容易です。
デメリット
粘土瓦は初期費用が高く、重量があるため耐震性に配慮が必要です。また、専門的な技術が必要なため施工できる業者が限られる上、台風や地震でズレや割れ、固定用の漆喰やモルタルの剥がれが生じることがあります。
耐用年数の目安とメンテナンス方法
粘土瓦自体の耐用年数は50年以上と非常に長く、適切なメンテナンスを行えば半永久的に使用できると言われています。
主なメンテナンスとしては、棟瓦の固定や防水に使われているモルタルや漆喰の補修・詰め直しが10〜20年ごと、漆喰の劣化が激しい場合や棟瓦を固定している銅線が切れた場合は棟瓦の積み直しが20〜30年ごとに行われます。
また、強風などで瓦がズレたり割れたりした場合は部分的に差し替えが必要です。瓦の下に敷かれている防水シートは瓦本体よりも寿命が短く、約20〜30年で劣化し雨漏りの原因になるため、葺き替えや大規模メンテナンス時には状態確認と交換が重要です。
注意点
粘土瓦は非常に長持ちしますが、下地の防水シートは20〜30年で劣化するため、定期的な点検と必要に応じた交換が必要です。また、近年では軽量瓦や防災瓦といった耐震性の高い瓦も普及しており、瓦の固定方法も進化して耐風性・耐震性が向上しています。
アスファルトシングル

アスファルトシングルは、ガラス繊維などの基材にアスファルトを浸透させ、表面に石粒を圧着して作られたシート状の屋根材です。
北米では100年以上の歴史があり、住宅用屋根材として広く普及しています。日本でも、そのデザイン性や施工性の良さから、洋風住宅を中心に採用が増えています。
メリット
アスファルトシングルのメリットは、軽量で耐震性に優れ、デザインや色のバリエーションが豊富な点です。複雑な屋根形状にもフィットしやすく、防水性も高く、比較的安価で施工しやすい屋根材です。また、柔軟性があるため衝撃に強く割れにくいという利点もあります。
デメリット
アスファルトシングルは、強風で剥がれやすく、表面の石粒が経年で剥離することがあります。また、他の屋根材に比べて耐用年数がやや短い傾向にあります。
耐用年数の目安とメンテナンス方法
アスファルトシングルの耐用年数は約15〜30年で、製品グレードや施工品質、立地条件によって異なります。メンテナンスとしては5〜10年ごとの定期的な点検で浮きや剥がれなどをチェックし、軽微な場合は部分補修を、必要に応じて接着剤を再塗布します。耐用年数を迎えた場合や広範囲な劣化が見られる場合は、葺き替えまたはカバー工法を検討します。
注意点
アスファルトシングルは、施工品質によって耐久性が大きく左右されます。特に雨仕舞が不適切だと雨漏りのリスクが高まるため、信頼できる専門業者を選ぶことが重要です。DIYでの施工は推奨されません。
また、製品によって品質にばらつきがあるため、保証内容や実績を確認し信頼できるものを選びましょう。台風が多い地域では、耐風性能の高い製品を選び、メーカー指定の施工基準を守ることが大切です。
セメント瓦

セメント瓦はセメントと砂を主原料として成形した瓦で、コンクリート瓦(モニエル瓦が有名)も同様のセメント系瓦の一種です。
かつては洋風住宅を中心に広く普及しましたが、近年はスレート屋根や金属屋根に押され、新築での採用は減少傾向にあります。
メリット
セメント瓦は製造時に着色されるためデザインやカラーが豊富で、洋風のデザインに合うものが多くあります。また、ある程度の厚みと重量感があり、しっかりとした印象を与えます。過去には、日本瓦に比べて安価に施工できる製品もありました。
デメリット
セメント瓦は定期的な塗装メンテナンスが必須で、瓦自体には防水性がありません。表面の塗装によって防水性と美観を保っているため、塗装が劣化すると瓦自体が水を吸い込み、脆くなったり、カビや藻が発生しやすくなります。そのため、約10〜15年ごとの再塗装が不可欠です。また、塗装が剥がれると瓦本体の劣化が急速に進み、割れや欠けの原因となります。
耐用年数の目安とメンテナンス方法
セメント瓦の耐用年数は約20〜30年ですが、これは定期的な塗装メンテナンスを行った場合の目安です。メンテナンスとしては、約10〜15年ごとの塗装、棟の補修、割れやズレの補修が必要です。
劣化が激しい場合や補修部品が入手できない場合は、葺き替えやカバー工法を検討する必要があります。
注意点
セメント瓦、特にモニエル瓦の塗装は専門的な知識と経験が必要です。適切な業者を選ばないと、塗膜がすぐに剥がれてしまう可能性があります。また、廃盤になっている製品が多いため、瓦が割れても同じものを見つけるのが難しく、部分補修ができない場合は葺き替えが必要になることがあります。
地域・立地条件に合わせた最適な屋根材は?

本は南北に長く、地域によって気候条件が大きく異なります。また、都市部と郊外、海沿いと山間部など、立地によっても住まいに求められる性能は変わってきます。
ここでは、地域や立地条件に合わせて最適な屋根材の選び方をするためのコツをご紹介します。
【気候条件別】おすすめの屋根材
台風が多い地域
台風が多い地域では、屋根材の耐風性能が重要です。瓦を釘で固定する防災瓦や耐風設計されたスレート屋根などが推奨されますが、施工方法や下地材も耐風性に影響するため、選定の際にはそのエリアの過去の被害事例を熟知している専門業者の意見を参考にしましょう。
雪が多い地域
積雪量の多い地域では、耐雪性能と雪処理を考慮した屋根材選びが重要です。金属屋根(ガルバリウム鋼板など)は表面が滑らかで雪が滑り落ちやすく、周囲に落雪スペースが確保できる場合には積雪荷重を軽減できます。瓦屋根の場合は材料自体の重量がありますので、雪の重みに耐える構造と適切な勾配設計が不可欠です。
暑さが厳しい地域・寒さが厳しい地域
厳しい暑さや寒さに対処するには、断熱性や遮熱性の高い屋根材を選ぶことが重要です。暑さ対策には、遮熱塗料を施した金属屋根、断熱性の高い日本瓦などが有効です。
寒さ対策には、これらの断熱対策に加えて気密性の高い施工が重要となります。ただし、断熱性能は屋根材だけでなく、屋根全体の構造によって大きく変わる点に注意が必要です。
沿岸部
海に近い地域では塩害が発生しやすく、金属系の屋根は錆びやすいことに注意が必要です。そのため、スレート屋根や瓦屋根、アスファルトシングルなどが推奨されます。
まとめ
屋根材選びで後悔しないためには、初期費用だけでなく、耐久性やメンテナンス性、地域の気候条件、デザイン性、将来のライフサイクルコストを総合的に考慮することが大切です。
また、どんなに良い屋根材を選んでも、質の高い施工を行う専門業者選びが重要です。信頼できる業者に相談し、安心して任せられるパートナーを見つけることが、屋根リフォーム成功の秘訣と言えるでしょう。
京都市近郊で屋根の状態が気になる方や、どの屋根材が良いか迷っている方は、地域密着型の屋根工事専門店「Re,ルーフ」にぜひご相談ください。
〈屋根材についての豆知識〉