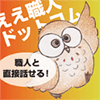台風後に増える「飛来物による屋根破損」応急処置と修理の流れとは
2025/08/21
日本は毎年発生する台風の通り道になっており、河川の氾濫や土砂崩れなど、生活に多くの被害をもたらします。大雨にともなう暴風で住宅に被害を及ぼすケースもあり、そのなかでも見落とされがちなのが「飛来物による屋根の破損」です。瓦のような頑丈な屋根材であっても、暴風による飛来物の衝突でヒビが入り割れるケースもあるため、どのような種類の屋根材であっても破損の被害が出る可能性はあります。この記事では、飛来物による屋根破損の応急処置と修理の流れを中心に、業者選びのポイントや保険活用のポイントなども詳しく解説します。台風による被害が起こりやすい地域にお住まいの方や、屋根の応急処置・修理の流れを知りたい方はぜひ参考にしてください。
様々なものが飛散する台風の風速は?

北西太平洋または南シナ海に存在する熱帯低気圧のうち、低気圧域内の最大風速がおよそ17m/s以上のものを「台風」と呼びます。気象庁によると台風の強さを表す表現には次の3つの階級があります。
| 階級 | 最大風速 |
| 強い | 33 m/s(64ノット)以上~44 m/s(85ノット)未満 |
| 非常に強い | 44 m/s(85ノット)以上~54 m/s(105ノット)未満 |
| 猛烈な | 54 m/s(105ノット)以上 |
最も下の階級である「強い」台風は、最大風速33m/s以上~44m/s未満です。これは、細い木の幹が折れ看板が落下・飛散、屋根瓦が剥がれ初めるなどの被害が出る強さです。つまり、勢力が「強い」以上の階級を持つ台風が過ぎ去った後には、住宅に何かしらの被害が出ているケースが多く、修理や応急処置が必要になる可能性が高いと言えます。
どのような飛来物があるのか
「強い」以上の勢力を持った台風は様々なものを飛散させ、屋根や外壁、窓などを破損させるほどの威力を持つ場合もあります。代表的な台風の飛来物には次のようなものがあります。
✔折れた木の枝、倒木
✔看板や立て看板の支柱
✔鉄や木でできた物干し竿
✔隣家の瓦やトタン、パネル
✔プランター、バケツ、ベンチなどの庭用品
✔ゴミ箱、ビニール袋、ベランダの椅子など
これらは一見軽そうな物でも、強い風速で飛ばされた場合、重さ以上のエネルギーを得るため、住宅の屋根などの硬いものを簡単に突き破ることがあります。
屋根破損のパターン

飛来物による屋根破損は、その種類や衝突の角度によってさまざまなパターンがあります。最も一般的なのは瓦のずれや割れで、特に棟瓦や軒先の瓦が被害を受けやすい傾向があります。雨樋の損傷も頻発し、飛来物の直撃により変形や破損、取付金具の外れが生じます。屋根材の剥がれは、スレート屋根や金属屋根で多く見られ、一枚が剥がれると連鎖的に被害が拡大することがあります。防水シートの破れは外観からは分かりにくいものの、雨漏りの直接的な原因となるため注意が必要です。これらの破損は単独で発生することもあれば、複数が同時に起こることも珍しくありません。
台風後にまずやるべき応急処置
台風通過後に屋根の状態を確認するのはとても大切ですが、最も優先すべきは「自分の安全」です。無理に屋根に上がったり、破損箇所を手で触ったりすることで、落下事故や感電事故につながることがあります。
【チェックポイント】
強風がまだ残っていないか?
屋根の上は濡れていないか?
周辺に電線や倒木はないか?
屋根に登る必要があるかどうか?
可能であれば、専門業者が来るまで屋根に登らず、地上からの目視や双眼鏡、スマホのズーム機能などで被害状況を確認しましょう。
応急処置に必要な道具
応急処置を行うには、最低限以下のような道具があると安心です。
・大きめのブルーシート(防水タイプ)
・土のう袋または重石(シート固定用)
・ガムテープ・防水テープ
・長い棒(突っ張りや確認用)
・軍手、安全靴、ヘルメット
・カメラまたはスマホ(記録用)
ブルーシートはホームセンターなどで売られている厚手のものを選ぶと、防水性が高く耐久性もあります。薄手のシートは風で破れやすく、長期使用には向いていません。
応急処置の手順
応急処置は次の手順で行います。
被害箇所の記録
破損した屋根の写真を複数の角度から撮影します。これは保険申請や修理見積もりに役立ちます。
破損部位をシートで覆う
雨水が浸入しないように、ブルーシートで屋根の破損部分を大きめにカバーします。余裕を持たせて覆うことで、雨が侵入しにくくなります。
固定する
土のうやブロックなどでシートの四隅をしっかり固定します。風が強くなっても飛ばされないように注意しましょう。テープで一時的に補強しておくと安心です。
屋根に登れない場合
無理に屋根に登らず、できる範囲で被害箇所を保護しましょう。雨漏りが発生している場合は、室内にバケツを置く、防水シートを天井裏に敷くなどの対策を行います。
修理の流れと信頼できる業者選びのポイント

応急処置を施した後は、なるべく早く修理業者に連絡をとり、修復作業を進めていく必要があります。以下が一般的な流れです。
修理までのステップ
業者に連絡・現地調査の依頼
屋根修理専門の業者や地元の工務店に連絡し、現地調査を依頼します。調査後に被害の範囲や修理内容を説明してもらいましょう。
見積もりを取得
複数の業者から見積もりを取り、金額や内容を比較するのが理想です。「屋根全体の葺き替えが必要」と言われた場合は、その理由を詳しく聞きましょう。
火災保険の申請(必要に応じて)
保険適用が可能な場合、修理前に保険会社へ連絡を取り、必要書類を準備します。
工事契約と施工
保険会社の査定が完了し、補償内容が確定したら、業者と契約を結び修理を進めます。契約内容には工事期間・費用・保証内容などを明記するようにしましょう。
修理完了・引き渡し
修理後は現場を確認し、問題がなければ完了です。施工内容によっては保証が付く場合もあるので、書面で確認しましょう。
業者選びのポイント
地域密着で実績のある業者を選ぶ
地元で長年営業している業者は信頼度が高く、緊急時の対応も早い傾向があります。
屋根工事の資格・許可を持っているか
「建設業許可」「瓦屋根工事技士」「屋根診断士」などの資格保有者がいる業者は安心です。
見積書が詳細で明確か
一式表示ばかりの見積書には注意。内訳が詳細に記載されているか確認しましょう。
アフターサービスがあるか
修理後の保証内容や、トラブル対応についても事前に確認しておくと安心です。
修理工程と期間
屋根修理の工程は被害の程度によって大きく異なりますが、一般的な流れは現地調査、詳細見積もり、材料調達、足場設置、既存部材撤去、新規材料設置、清掃、完了検査の順に進みます。部分的な瓦の交換であれば1〜2日で完了しますが、広範囲の屋根材交換や下地修理が必要な場合は1〜2週間を要することもあります。工事期間中は騒音や粉塵が発生し、日常生活に影響が出ることを覚悟しておく必要があります。また、雨天時は作業が中断されるため、天候によって工期が延長される可能性もあります。
火災保険会社への連絡
台風による被害は、火災保険の「風災」補償の対象となることがほとんどです。まずは契約している保険会社に連絡し、被害状況を伝えて指示を仰ぎましょう。保険会社への連絡は、修理業者への依頼と並行して行うのが効率的です。必要な書類(見積書、被害写真など)を保険会社に提出し、鑑定人が現地調査を行うこともあります。この一連の手続きをスムーズに進めるためにも、信頼できる修理業者と連携することが大切です。
火災保険活用のポイント
台風被害による火災保険活用は、次の3つのポイントが大切です。
風災補償の確認: 契約内容に「風災」が含まれているか、また「免責金額」(自己負担額)がいくらかを確認しておきましょう。
申請のタイミング: 被害発生から3年以内に申請する必要があることが一般的ですが、早めの申請を心がけましょう。
経年劣化との線引き: 保険金はあくまで「台風による被害」に対して支払われます。単なる経年劣化と判断された場合は補償の対象外となることがあります。そのため、被害が台風によるものであることを明確に示す写真や証拠が重要になります。
保険金申請の一般的な流れ
保険金申請の一般的な流れは次の通りです。
①保険会社へ被害報告。
②保険会社の指示に従い、修理業者から見積もりを取得。
③必要書類を保険会社に提出。
④鑑定人による現地調査(省略されることもあります)。
⑤保険金額が確定し、指定の口座に保険金が支払われる。
予防策と今後の備え
台風被害を最小限に抑えるには、日頃からの予防対策が重要です。年に1〜2回の定期点検により、瓦のズレや雨樋の詰まりなどを早期発見し、小さな不具合のうちに修理しておくことで大きな被害を防げます。また、築年数が古い住宅では、耐風性を向上させるための改修工事も検討に値します。台風シーズン前には、庭の木の剪定や物置の固定、ベランダの片付けなど、飛来物となりうる要素を事前に除去することも効果的な予防策です。
まとめ
この記事では、飛来物による屋根破損の応急処置と修理の流れを中心に、業者選びのポイントや保険活用のポイントなども詳しく解説しました。強い勢力を持った台風は様々なものを飛散させ、住宅屋根にも爪跡を残します。屋根が劣化し傷んでいる状態では被害が大きくなりやすいため、屋根を健康な状態に保つための定期点検がおすすめです。また、屋根が損傷を受けた際に写真などを残さず修復した場合には、火災保険での補償申請が通らない場合もあります。事前に保険会社へ連絡したり写真を残したりすることを忘れないようにしましょう。
Re,ルーフは京都市の屋根工事職人直営店です。台風が増えるシーズンは住宅被害の修理依頼が殺到しやすいため、早めのご依頼がおすすめです。お見積もりから対応可能ですので、お気軽にご連絡ください。