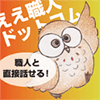ゲリラ豪雨で被害が増加中!台風・豪雨に強い屋根構造とは?
2025/07/31
近年、局地的なゲリラ豪雨が増えており、雨漏りなど屋根を中心に被害が出るケースが増加しています。また、台風によって屋根材が飛ばされたり、屋根の一部が破損するケースも多く、台風やゲリラ豪雨に強い屋根構造を求める声が高まっています。この記事では、台風・豪雨に強い屋根構造や屋根材、被害の種類や台風・豪雨への対策法などを解説します。台風豪雨に強い屋根構造を知りたい方や、新築を検討している方、台風が多く通過する地域にお住まいの方はぜひ参考にしてください。
台風・豪雨に強い屋根の基準は?
台風・豪雨に強い屋根とは、台風や豪雨に見舞われた際に損傷しない造りになっている屋根です。建築基準法では、台風などの暴風に対して耐えうる住宅を建築するように「耐風等級」と言った基準が設けられています。耐風等級には等級1と2があり、どのような住宅でも最低限の基準として耐風等級1を満たした構造計算に基づいて建築されています。なお、等級1は「稀に(50年に一度程度)発生する暴風による力に対して損傷を生じない程度」と定められており、「稀に発生する暴風」とは高さ10mの位置で平均風速約30m/s・瞬間最大風速45m/sの風を指します。気象庁による台風の強さに照らし合わせると、3段階のうち2段階目の「非常に強い(最大風速44 m/s以上~54 m/s未満)」に相当します。つまり、「非常に強い台風」に見舞われると、住宅に損傷が起こる可能性があります。
台風・豪雨で多い屋根への被害

台風・豪雨では、次のような屋根への被害が多くなります。
✅屋根材の飛散
台風による強い風の被害で多くの方がイメージしやすいのが、屋根材の飛散ではないでしょうか。多くの住宅の屋根材は、ある程度の強風に耐えられるように施工されていますが、極端に劣化が進んでいたりすると屋根に留まる力が弱まり、強い風で飛散しやすくなります。
✅屋根の破損
屋根材の飛散と合わせて、下地材である野地板などの屋根そのものが破損するケースもあります。破損しやすい箇所は、風が回り込みやすい軒先や破風板(はふいた)、ケラバ、屋根の最も高い位置である棟部です。
✅雨漏り
台風による豪雨では、雨漏りも起こりやすい被害の一つです。普段の雨と異なり強い風を伴うため、劣化した屋根材やシーリングの隙間から雨水が侵入しやすい傾向にあります。
台風・豪雨に強い屋根構造・形状の比較
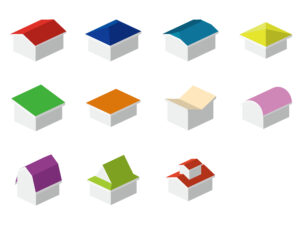
屋根の形状にはいくつかの種類がありますが、多くの住宅に採用されている次の5つの屋根の形状について比較します。
・切妻屋根
・寄棟屋根
・方形屋根
・片流れ屋根
・陸屋根
切妻屋根
切妻屋根は、2枚の屋根面が合わさった形状の屋根で、三角屋根と呼ばれることもあります。シンプルな形状で屋根の継ぎ目が少ないため、雨漏りを起こしにくく豪雨に強い形状と言えます。屋根の傾斜方向への風に対して影響を受けにくい特徴がありますが、傾斜方向ではない風に対してはあまり強くありません。
寄棟屋根
4つの屋根面が合わさった形状の屋根で、屋根の頂上は一本の棟になっています。4方向に延びた屋根の傾斜が台風の風圧を受け流すため、耐風性が高い屋根と言えます。また、雨水の排水性も良いため、全体的に台風・豪雨に強い屋根構造と言えますが、切妻屋根ほどシンプルな構造ではないため、定期的に点検を行い屋根材や棟部を劣化させないようにしましょう。
方形屋根
方形屋根は、頂点から同じ角度で4つの屋根面が伸びている形状の屋根です。ピラミッドのような形をしている方業屋根は、構造が丈夫で耐風性・排水性に優れており、台風・豪雨に強い屋根です。屋根面の合わせ目が多いため、寄棟屋根と同じように定期的に点検を行い、雨漏りを起こさせないようにしましょう。
片流れ屋根
一方向のみに傾斜が付いている屋根です。モダンでスタイリッシュな雰囲気の屋根形状ですが、一方向のみに屋根傾斜が付いているため、傾斜面以外の方向から吹く風に弱く、耐風性は高くありません。また、シンプルな構造で排水性は高いですが、屋根の頂部(棟部)から雨水が侵入しやすく、比較的雨漏りが起こりやすい特徴があります。片流れ屋根は、台風・豪雨に強い屋根とは言えません。
陸屋根
屋根面が水平でフラットな屋根です。屋上として利用できる陸屋根は、マンションなどの屋根に多く、屋根の積雪を地面に落としたくない場合にも採用されます。平らな屋根は風の影響を受けにくいため耐風性は高いですが、雨水を排水する能力が低く、屋上部分の防水層が劣化すると雨漏りを起こす原因になります。
台風・豪雨に強い屋根材の比較

屋根に使用する屋根材によっても、台風・豪雨への強さは異なります。ここでは、採用率の高い3つの屋根材について比較します。
①瓦屋根
瓦屋根は、さまざまな屋根材の中でもっとも重量が重いため、風によって屋根全体が浮き上がりにくい特徴があります。また、非常に高い耐久性を持ち、劣化しにくいため長期間にわたって厳しい気象条件に耐えることに加え、屋根へ階段のように重ねて葺くため、雨を効果的に排水できる特徴もあります。ただし、屋根に固定されていない部分が多く、風速20m/s以上の非常に強い風が吹くと飛散する恐れがあるため、台風に弱い一面もあります。台風に強い瓦を求める場合には、屋根へ釘やビスで固定する「防災瓦」を選ぶと良いでしょ
②ガルバリウム鋼板屋根
薄く軽量な鋼板でできたガルバリウム鋼板屋根は、ビスによって全体がしっかり固定されているため、屋根材1枚1枚が飛散する心配がなく、台風に強い屋根です。また、表面が滑らかで耐久性・耐水性・排水性が高く、雨漏りを起こしにくいため、豪雨にも強い特徴があります。弱点の少ないガルバリウム鋼板屋根は、台風・豪雨に強い屋根と言えます。
③スレート屋根
セメントを薄い板状にしたスレート屋根は、屋根に釘やビスで固定されていますが、比較的軽量なため、台風で飛散しやすい屋根材です。特に、劣化が進行するとひびが入りやすく割れやすいため、飛散するリスクが高まります。また、塗装によって耐水性を確保しているため、定期的に塗装メンテナンスを行わないと雨漏りを起こすリスクも高まります。スレート屋根を台風・豪雨に強い状態に保つには、メンテナンスを怠らないことが重要です。
台風で屋根が飛ばされないようにする対策

台風による暴風で屋根が飛ばされないようにするには、次のような対策が効果的です。
✅屋根材の割れやズレを確認
屋根材にズレやひび、割れなどがない状態に保つことが耐風性を高める上で大切です。どのような屋根材も状態が良ければ、耐風等級によってある程度の強風に耐える力を持っています。ズレやヒビ、割れがあると隙間から風が入り込み、屋根材を浮かせる力が働くため、飛散するリスクが高まります。
✅棟板金をしっかり固定する
屋根の頂上にある棟板金は、数年で固定する釘が抜けてくるため、浮きやすくなります。浮いた隙間に風が入り込み、棟板金や屋根材が飛散しやすくなるため、しっかりと固定されているか数年おきに確認しましょう。
✅軒の長さを考慮する
軒は雨水の侵入を防ぐ重要な部分ですが、長いと下方向から吹き上げる風を受けやすくなります。後から軒の長さを変更することは難しいため、台風に強い住宅にしたい場合は、新築時に軒の長さを考慮すると良いでしょう。
豪雨による雨漏りを防ぐ対策

台風がもたらす豪雨による雨漏りを防ぐには、次のような対策が有効です。
✅屋根材や防水シートを良い状態に保つ
屋根材が劣化すると隙間から防水シートへ雨水が流れ込みます。防水シートが劣化して穴や亀裂ができると、雨水が野地板に流れてしまい雨漏りを起こします。防水シートを劣化させないためには、屋根材を劣化させないことが大切です。屋根からの雨水の侵入を防ぐため、定期的にメンテナンスを行い屋根材や防水シートを良い状態に保ちましょう。
✅棟瓦・棟板金・谷板金の状態を確認
棟瓦・棟板金・谷板金は屋根同士の隙間を覆い隠すと共に、雨の侵入を防ぐ役割があります。棟瓦は地震によってズレたり、劣化した漆喰の隙間から雨水が侵入しやすい特徴があり、棟板金は固定釘が抜けて隙間が生まれやすく、谷板金は錆や隙間のシーリングが劣化しやすい特徴があります。これらの不具合を起こしやすい特徴に注意して、定期点検などで早めに補修してもらうように心がけましょう。
✅雨樋の排水能力は十分か
雨樋が破損していたり詰まりを起こしていたりすると、本来の排水能力を発揮できません。雨樋から雨水が溢れると思わぬ場所へ雨水が流れ、外壁やサッシの隙間などから屋内に侵入して雨漏りを起こす可能性があります。雨樋の破損やゆがみ、詰まりを見つけたら早めに修理してもらうようにしましょう。
まとめ
この記事では、台風・豪雨に強い屋根構造や屋根材、被害の種類や暴風・豪雨への対策法などを解説しました。台風・豪雨に強い屋根構造・形状は、4つの屋根面が合わさる「寄棟屋根」「方形屋根」です。台風・豪雨に強い屋根材は、ガルバリウム鋼板屋根です。ただし、いかなる屋根構造・屋根材であっても、劣化が進んでいれば本来の性能を発揮できません。台風・豪雨に備えるためにも定期点検を行うようにしましょう。
京都市を中心に屋根修理を手掛ける株式会社Re,ルーフは、職人直営の屋根修理専門店です。台風が通過した後には業者への修理依頼が増えるため、実際に修理ができるまでお待たせしてしまう可能性があります。普段から定期的にメンテナンスを行うことで、屋根を健康な状態に保ち、台風の被害を最小限に抑えられます。長い間、定期点検を行っていない住宅にお住まいの方は、ぜひRe,ルーフへお任せください。ご連絡お待ちしております。