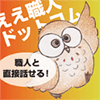京町家リフォームで多い屋根トラブルとは?古民家再生の注意点
2025/10/15
京町家のリフォームを行う場合は、建築基準法への適合や京都市景観条例の遵守など様々な課題をクリアしなければなりません。
屋根のリフォームでも、使える屋根材が制限されていることがあるので、リフォーム工事を行う前に、入念に計画を立てる必要があります。
京町家の屋根のリフォームを行う際の注意点を解説します。
京町家とは?

京町家は、京都市内の伝統的な木造家屋で、間口が狭く奥行きが深い「うなぎの寝床」と呼ばれる特長の作りになっています。
屋根も特徴的で、むくり屋根と言い、屋根全体がなだらかな凸状の丸みを帯びた形状になっていて、魔除けとして、鍾馗さんが設置されていることが多いです。
また、軒先が一文字瓦となってまっすぐな直線になっていることが多いです。
このように京町家には、現在の住宅には見られない様々な特徴があります。
京町家の屋根リフォームで注意したいことは
京町家には、1950年(昭和25年)の建築基準法施行以前に建築されたものもあります。
こうした京町家のリフォームを行う場合には原則として、現在の建築基準法に適合させなければなりません。
しかし、建築基準法に適合させた場合は、京町家の特徴が失われてしまいます。
そこで、京都市独自のルールである「建築基準法の適用除外制度」を活用することによって、京町家の外観を保存しながらリフォームする事を検討しましょう。
屋根のリフォームについては、屋根の下地を含めた全面的なやり替えの工事については、建築基準法の適用対象になります。この場合は、建築基準法の適用除外制度を活用することで、京町家の外観を維持することができます。
一方、瓦、野地板の葺き替えや垂木の修繕だけであれば、屋根を構成する部材の一部の補修なので、大規模の修繕に当たらず、建築基準法の遡及適用を受けません。そのため、京町家の外観を維持したままのリフォームが可能です。
京町家の屋根リフォームでも現在の規制に適合させた方がよい点
京町家の屋根リフォームでは、京町家の外観を維持することができますが、一方で、現在、建築基準法で求めている規制に適合させた方がよい点もあります。
瓦の緊結
瓦の緊結方法については、令和4年1月1日から強化されています。強風による屋根瓦の飛散や落下を防止するためです。建築基準法の遡及適用を受けない場合は、対応する必要はありませんが、できれば対応した方が安心です。
軒裏の防火構造(準耐火構造)化
京町家の軒裏は、垂木や野地板の木材が見える構造になっています。
しかし、建築基準法では、軒裏の部分は防火構造とすることが求められています。一般的な建築では、この部分にケイカル版等を施工することが多いですが、京町家でこれを張り付けると意匠性が失われてしまいます。
ただ、木材あらわし軒裏でも準耐火構造とすることが可能なので、国土交通省告示仕様に対応した方法で施工した方が安心です。
現在では、不燃木材もあるので、こちらを用いるのもよいでしょう。
京町家の屋根リフォームが必要になるケースとは?

京町家の屋根は、そのほとんどが和瓦でできています。和瓦は、寿命が50年から100年程度もあり、寿命が非常に長いです。
和瓦が割れてしまうことはめったになく、和瓦の劣化が雨漏りの原因になることは少ないと言えます。
それでも、雨漏りが発生することはあります。
✔瓦にずれが生じた場合
瓦は、桟木に引っかけるようにして葺いていますが、すべて緊結されているわけではありません。軒、けらば、棟だけ緊結していて、平部の大半は緊結していないこともあります。
そのため、台風や地震の被害によってずれが生じてしまうことがあります。
瓦にずれが生じると、その隙間から雨水が染み込むようになって、雨漏りの原因となってしまいます。
✔瓦が破損した場合
瓦はかなり頑丈ですが、飛来物が当たった場合は、破損してしまうことがあります。
台風の際に物が飛んできて、屋根にぶつかった場合が代表例です。
この場合も、破損した部分から雨水が染み込むようになって、雨漏りの原因となってしまいます。
✔漆喰の劣化や剥がれが生じた場合
瓦の棟部分には、漆喰が埋められています。
棟瓦と平瓦の境目には、三日月状の隙間がありますが、この部分を塞いでいるのが漆喰です。
屋根に使う漆喰の寿命は、10年から20年程度なので、この部分に劣化が確認された場合は補修が必要です。
漆喰の劣化を放置していた場合はやがて剥がれてしまい、雨水が染み込んだり、棟の土台が崩れて、棟部分の崩れにつながってしまう恐れがあります。
✔防水シート(ルーフィング)が傷んでいる場合
屋根からの雨漏りは瓦だけで防いでいるわけではありません。
瓦には隙間があり、ある程度の雨水が染み込むことは避けられません。ただ、その下に防水シート(ルーフィング)が敷設されているおかげで、室内への雨漏りを防いでいるわけです。
この防水シートは、耐用年数が20年程度となっています。
瓦には異常がなくても、防水シートが劣化していると雨漏りの原因となってしまうので、定期的に瓦の葺き直し工事を行うと共に、防水シートも交換する必要があります。
✔野地板が傷んでいる場合
防水シートが傷んでいると、下地の板材である野地板も雨水を吸って劣化してしまいます。
野地板が劣化すると腐ってしまい、最悪の場合は、屋根の崩落につながってしまいます。
そうなる前に、野地板も含めた全面的な屋根リフォームを行うことが重要です。
京町家の屋根リフォーム方法

京町家の屋根のリフォーム方法はいくつかありますが、どこを補修するのか、既存の瓦を再利用するのかにより異なります。
✔漆喰の補修のみを行う場合
屋根の傷みが漆喰の劣化に留まる場合は、漆喰の補修のみで済ませることも可能です。
漆喰がひび割れていたり、変色しているという程度の場合です。
漆喰が全体的に剥がれていて、棟瓦に崩れなどが見られる状態の場合は、漆喰の補修だけでなく、棟部分を解体して葺き直しが必要になります。
✔葺き直し工事
既存の瓦を再利用して、屋根を全面的にリフォームする場合は、葺き直し工事で対応することができます。
ただ、瓦の中には劣化したり、割れているものがある場合もあるため、新しい瓦との交換が必要になる部分が生じることもあります。
葺き直し工事では、瓦をすべて外したうえで、瓦を引っかける桟木を外し、防水シート(ルーフィング)も交換します。
野地板の状態も確認し、劣化している場合は、野地板の交換も行います。
野地板がバラ板の場合は、構造的に弱いため、構造用合板の野地板に交換した方がよいです。
下地の工事が終わったら、外した瓦を丁寧に葺き直します。
葺き直し工事は、既存の瓦を生かせるので、エコなリフォーム工事と言えます。
✔葺き替え工事
葺き替え工事は、既存の瓦を撤去して新しい屋根材を葺く工事です。
屋根のリフォーム工事の方法として、既存の屋根材の上に新しい屋根を被せるカバー工法という方法がありますが、瓦屋根の場合はこの工法を採用することはできません。
新しい屋根材に替えたい場合は、瓦を撤去するのが基本です。
瓦を撤去して下地の状態にしてから、防水シート(ルーフィング)と野地板の交換を行います。
新しい屋根材は、新たに瓦を調達することもできますし、瓦以外の屋根材に替えることも可能です。
例えば、軽量な金属屋根に交換することは、耐震性を高めるうえで有効です。
屋根の葺き替え工事では京都市景観条例に注意
京都市では、伝統的な街並みを維持するために、建物を建てる際に京都市景観条例を遵守することが求められています。
屋根についても、細かいルールが設けられています。
主なルールを挙げると次のとおりです。
・屋根の形式は勾配屋根を基本とする。(切妻屋根、寄棟屋根、入母屋屋根など)
・屋根の軒やけらばの長さが決まっている。
・屋根の色彩は、瓦なら「いぶし銀」、銅板は「素材色又は緑青色」、金属屋根などは「光沢のない濃い灰色、光沢のない黒」とする。
・屋根材は、日本瓦、銅板、金属板が原則。
こうした屋根の規制については、美観地区(山ろく型、山並み背景型、岸辺型、旧市街地型、歴史遺産型、沿道型)と美観形成地区とで、厳しさが異なります。
美観地区の場合は、かなり厳しい規制が設けられているため、建築できる屋根が限定されます。
まずは、お客様がお住まいの地域がどの景観地区に該当するのかを調べて、詳しい規制内容を確認することが大切です。
まとめ
京町家のリフォーム工事を行う場合は、建築基準法に適合させることや京都市景観条例を遵守するなど、様々な点を考慮しなければなりません。
そのためには、京都の伝統的な建築にも詳しく京町家のリフォームの経験が豊富な業者に依頼することが大切です。
株式会社Re,ルーフには、京都の伝統的な建築にも詳しく、京町家のリフォームの経験が豊富な職人が在籍しております。
京町家の屋根のリフォームを検討されている方は、お気軽にご相談ください。