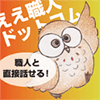雨漏り放置がもたらす二次被害とは?シロアリ・カビ・構造劣化の危険性
2025/09/17
雨漏りしても、壁や床を雑巾などで拭いたり、バケツを置いておけば大丈夫と思っていませんか。
雨漏りによる一次被害は大したことがなくても、雨漏りを放置した場合は、建物の柱や梁が腐ってしまう、シロアリ、ダニ、カビが繁殖してしまうといった二次被害が生じてしまいます。
この記事では、雨漏り放置がもたらす二次被害とはどのようなものなのか解説します。
雨漏りした場合の被害とは?

雨漏りが発生した場合、家の中が水浸しになったり、家具が濡れてしまうといった被害を受けてしまいます。
具体的には次のような被害です。
・壁が濡れてしまう。
・カーテンや壁に掛かっているものが濡れてしまう。
・床が水浸しになる。
・絨毯や畳などの床材がびしょびしょになってしまう。
・家具が濡れてしまう。
・タンスなどの中に入っている服なども濡れてしまう。
・家電が濡れて壊れてしまう。
・天井や壁などに雨染みができてしまう。
こうした被害は、雨漏りによる一次被害と言えます。
幸いにして、壁や床が濡れただけであれば、雑巾などで拭いたり、バケツを置いておけば、一次被害は少ないかもしれません。
しかし、それでも、雨漏りを放置してはいけません。
雨漏りの本当の被害は二次被害
雨漏りの本当に恐ろしい被害は、一次被害ではなくて、二次被害です。
二次被害は、雨漏りを放置したために、建物の強度が下落して建物の資産価値が下落するという形で現れます。
具体的なトラブルの事例は次のとおりです。
・建物の構造部分が腐ってしまう
・シロアリが繁殖してしまう
・ダニやカビが繁殖してしまう
・建物の資産価値が下落する
一つ一つ確認しましょう。
建物の構造部分が腐ってしまう
雨漏りを放置した場合、雨が降る度に建物内部が雨水によって湿った状態になってしまいます。
雨が続いた場合は全く乾燥せず、じめじめした状態になってしまいます。
木造住宅の場合、主要な構造部分は大半が木材で作られています。
木材は、水分に弱いため、乾燥した状態を保つことが非常に大切です。
雨漏りにより、構造部分の木材が、雨水を吸ってじめじめしたままの状態になってしまうと、木材腐朽菌が繁殖します。
特に、湿度85%、含水率25%の条件下で木材腐朽菌が繁殖しやすくなります。
柱や梁、壁といった構造部分の木材が木材腐朽菌によって腐ってしまうと、建物の強度は著しく低下してしまいます。
新築当初は耐震性が高い木造建築だとしても、主要な構造部分が腐っていては、十分な耐震性を発揮することができません。
更に腐食が進むと、突然、天井や床が抜けてしまったり、壁が崩落するといった形で地震が発生しないときでも被害が生じることがあります。
シロアリが繁殖してしまう
雨漏りを放置した結果、壁の内部の柱や板材がじめじめした状態になってしまうと、そうした湿気を好む害虫が発生しやすい状態になってしまいます。
特に恐ろしいのがシロアリです。
木造住宅にとってシロアリは大敵で、シロアリに侵食されてしまうと、木材の内部がスカスカになってしまい、強度が著しく低下してしまいます。
これを防ぐために、現在の建物の多くは、基礎を高くして、換気のよい状態を保てるようにしています。
また、土台から一定の高さには、シロアリを防ぐための薬剤を塗っています。
ところが、雨漏りにより、壁の内部の柱や板材が濡れてしまい、じめじめした状態になると、シロアリが寄り付きやすくなってしまいます。
特に、外壁や窓からの雨漏りが生じている場合は、土台部分まで雨水が浸入している可能性があるので、シロアリによる被害を受けやすくなります。
シロアリはどんな家でも発生する可能性があります。
ベタ基礎の場合は、床下に土はありませんが、ベタ基礎のコンクリートに全く隙間がないわけではありません。
水道やガスの配管、排水の配管のために、基礎の一部分には空洞が設けられています。その隙間からシロアリが侵入することがあるのです。
また、歳月が経って、ベタ基礎が傷んでひび割れが生じてしまうと、その隙間からも白アリが浸入することがあります。
家の周りがコンクリートでもシロアリは侵入してくるので油断はできません。
ダニやカビが繁殖してしまう
雨漏りを放置した結果、天井や壁の内部がじめじめした状態になるとダニやカビが繁殖しやすくなります。
ダニもじめじめした状態を好む害虫です。
布団でさえじめじめしていると、ダニが発生しやすくなるため天日干しが推奨されているほどです。
天井や壁の内部には断熱材が充填されていますが、この断熱材は雨漏りによって水分を吸ってしまい、じめじめしたままになってしまいます。この場合、ダニの好む環境になってしまい、ダニが発生しやすくなるわけです。
ダニに刺されるとかゆいだけでなく、様々なアレルギーを引きおこしたり、病気の原因となってしまいます。
また、天井や壁の内部がじめじめした状態になると内部でカビが繁殖しやすくなります。
カビが繁殖すると見た目が悪いだけではありません。
やはり、様々なアレルギーを引きおこしたり、病気の原因となってしまいます。
つまり、ダニやカビが繁殖することによって、不健康な住宅になってしまうということです。
建物の資産価値が下落する
雨漏りが生じることで、建物の資産価値は著しく下落します。
上記までに紹介したとおり、雨漏りを放置した場合、建物は深刻なダメージを受けてしまいます。
建物の構造部分が腐っている場合は、いずれ、建物が崩壊してしまう可能性さえあります。
こうしたこともあり、雨漏りが生じた建物の資産価値は著しく低下します。
建物をいずれ売って住み替えをしようと考えている方は、雨漏りを生じさせないように気を付けることはもちろんですが、万が一、雨漏りが発生したらすぐに、修理を行っておくことが大切です。
雨漏りによる二次被害を防ぐには?

雨漏りによる二次被害を防ぐための最善の方法は、雨漏りしたらすぐに、雨漏り修理を依頼することです。
床や壁が濡れただけで、室内で大した被害がなかったとしても、二次被害はじわじわと進行します。
早期に対処しておけば、少ない費用で修理できますが、二次被害が拡大してからだと、土台や柱の交換も必要になる等、建物を新築するのと同じくらいの費用が掛かってしまうこともあります。
雨漏りの点検方法
現在の住宅は、雨漏りが生じていても室内で、雨漏りに気づかないこともあります。雨漏りに気づいたときは、既に二次被害が生じてしまっていることもあります。
そのため、できるだけ早い段階で、雨漏りの予兆を掴むことが大切です。
外側からの雨漏りの点検
雨漏りは、建物の屋根や壁に隙間が生じてしまい、そこから雨水が浸入することによって発生します。
そのため、建物の屋根や壁に異常がないかどうか確認することが雨漏りを防ぐための第一歩になります。
屋根については次の点をチェックしましょう。
✔屋根材のズレや脱落部分はないか。
✔屋根材がひび割れしていないか。
✔屋根にコケや草が生えていないか。
✔雨樋が壊れていないか。
✔屋根瓦の漆喰部分が剥がれていないか。
✔板金に浮きや錆が生じていないか。
外壁については次の点をチェックしましょう。
✔外壁材にひび割れが生じていないか。
✔外壁材に欠けや剥がれは生じていないか。
✔外壁材に穴が開いていないか。
✔外壁材の塗装が剥がれたり、コケやカビが発生していないか。
✔コーキングの部分が劣化していないか。
窓枠やサッシまわりについては次の点をチェックしましょう。
✔窓枠やサッシまわりのコーキング部分が劣化していないか。
✔窓枠やサッシ周辺の外壁にひび割れが生じていないかどうか。
ざっと見て不安な点があれば、屋根工事業者などに一度点検してもらうとよいでしょう。
室内からの雨漏りの点検
室内から雨漏りの点検をする方法もあります。
屋根裏を点検できる場合は、屋根裏を見てみて、柱や梁、板材などが濡れていないかどうかチェックしましょう。
室内では次の点をチェックしましょう。
✔天井や壁に雨染みが生じていないか。
✔天井や壁のクロスが剥がれていないか。
✔天井や壁のクロスに黒カビが発生していないか。
✔かび臭いにおいがしないかどうか。
既に室内側に雨漏りが生じている場合は、雨染みの他、クロスが剥がれるという形で被害が生じることがあります。
クロスは、石膏ボードにのりで張り付けられていますが、雨漏り被害を受けることによって、接着力が弱まって剝がれやすくなります。
クロスの剥がれが目立つ場合は、雨漏りが生じている可能性を疑いましょう。
まとめ
雨漏りを放置した場合、建物が深刻な二次被害を受けてしまいます。
これを防ぐためには、雨漏りを生じさせないことや雨漏りした場合は早期に修理することが大切です。
Re,ルーフは、京都市右京区を中心に活躍する屋根工事職人直営店です。京都市や亀岡市などを中心に京都府全域で屋根工事や雨漏り修理工事を承っています。職人直営店なので、本当に工事に必要な費用だけで屋根工事や雨漏り修理工事を行うことができます。
ご自宅の雨漏りでお悩みの方はお気軽にご相談ください。