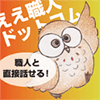屋根と谷樋の取り合い部は雨漏り多発ポイント!屋根職人が教える原因と対策
2025/11/11
屋根からの雨漏りは、屋根材の劣化によるものもありますが、最も大きな原因は、屋根の接合部分の劣化によるものです。
特に、屋根と屋根が取り合う部分にある谷樋(谷板金)と呼ばれる部位は、雨漏りの原因となりやすい箇所です。
屋根と谷樋の取り合い部が雨漏りの原因となる理由や雨漏りを防ぐための対策について解説します。
谷樋(谷板金)とは

谷樋は、谷板金とも呼ばれ、屋根と屋根が取り合う部分に設置されています。
樋という言葉から分かる通り、屋根の軒先に張り巡らされている雨樋と同じ役割を果たしています。
雨樋は、屋根を伝った雨水を受け止めて、排水口に流す役割を果たしています。
これによって、建物の周りに雨水による水たまりができてしまうことを防いでいます。
屋根と屋根が取り合う谷に設置されている谷樋も、屋根の高い位置から流れてくる雨水を受け止めて、軒先の雨樋に流す役割を果たしています。
谷樋(谷板金)と雨樋の違い
雨樋との違いは、雨樋が軒先に張り巡らされているため、異常があればすぐに気づきやすいのに対して、谷樋は屋根の下に埋め込まれているため、異常に気づきにくいことです。
そのため、雨漏りにつながるような劣化や異常が放置されてしまい、雨漏りの大きな原因になってしまうことが多いのが実情です。
谷樋(谷板金)がある屋根とは?
谷樋または、谷板金と呼ばれる部位がなければ、屋根と谷樋の取り合い部からの雨漏りを心配する必要はありません。
しかし、谷樋がない家を探す方が難しいかもしれません。
まず、谷樋がない家は、屋根が切妻、寄棟、片流れ、招き屋根などのシンプルな形状になっています。
そして、建物の平面の形状も完全な長方形、または正方形で、出っ張りがありません。
こうしたシンプルな構造の家であれば、谷樋が存在しないため、屋根からの雨漏りのリスクを大きく減らすことができます。
ところがこうしたシンプルな構造の家はあまりありません。
ほとんどの家は、玄関先が出っ張っていたり、平面の形状がL字型や凸型になっているはずです。
こうした家には、入隅部分に屋根と屋根の取り合い部分が生じ、谷樋が設置されています。
谷樋(谷板金)の劣化や異常とは?

雨漏りにつながる谷樋の劣化や異常とはどのようなものなのか解説します。
✅経年劣化
谷樋(谷板金)は、ガルバリウム鋼板などの比較的錆に強い金属板で作られています。しかし、永久に錆びないわけではありません。
谷樋は左右の屋根から雨水が集まる場所なので、水が溜まりやすく、湿った状態になりやすいです。
勾配が緩い場合は、雨水が流れきらずに濡れた状態のままになりやすいです。
こうした状況なので、谷樋は、錆が進行しやすい環境になり、他の部位の板金と比べても劣化が早くなります。
✅穴が開いてしまう
谷樋(谷板金)は、金属の板でできているため、錆が進行すると、穴が開いてしまいます。穴が開いてしまうと、そこから直接雨水が屋根の内部に浸入してしまい、雨漏りの原因になります。
そのため、錆びやすい環境にある場合は、錆に強いステンレスの谷板金を設置すべきです。
✅谷樋(谷板金)の歪みやズレが生じる
谷樋(谷板金)は、1枚の金属板だけで作られているとは限りません。谷樋が長い場合は、2枚の板金を重ね合わせる形で設置されていることもあります。
この場合、経年劣化が進むと、谷樋が歪んでしまい、隙間が生じるようになります。
その隙間の部分から、雨水が浸入し、雨漏りの原因になってしまうわけです。
✅ゴミが詰まることによるオーバーフローが生じる
谷樋(谷板金)が設置されている箇所は、名前の通り、谷状になっています。左右の屋根からは雨水だけでなく、ゴミも集まりやすい箇所です。
木の葉や枝のクズなどが、まとまって、谷樋に溜まってしまうと、雨水が流れにくくなってダムのような状態になってしまいます。
すると、雨水が谷樋から溢れて、屋根内部へと浸透してしまうわけです。
また、木の葉や枝のクズが溜まった部分は、常にジメジメした状態になり、錆の原因になってしまいます。
谷樋(谷板金)のメンテナンス方法

谷樋(谷板金)は、屋根の中でも特にメンテナンスが大切な部分です。
谷樋の通常のメンテナンス方法は、掃除と塗装です。
谷樋(谷板金)の掃除
谷樋(谷板金)は、ゴミが溜まりやすい箇所です。周辺に屋根よりも高い木がある場合は、木の葉や枝のクズが屋根に溜まりやすいです。
こうしたゴミが谷樋で固まってしまうと、オーバーフローし、雨漏りにつながってしまうため、定期的に掃除することが大切です。
なお、掃除の際は、屋根に上がっての作業になるため、慣れていない方は危険です。
無理せずに、屋根修理業者などに依頼してください。
谷樋(谷板金)の塗装
谷樋はガルバリウム鋼板などの錆びにくい金属で作られていることが多いですが、全く錆びないわけではありません。
錆が進行すると、穴が開いて雨漏りの原因になってしまうので、定期的に塗装して錆びないようにすることが大切です。
最低でも、10年に一度は、谷樋の塗装によるメンテナンスを行っておくべきです。
谷樋(谷板金)の修理方法
谷樋(谷板金)に穴が空いたり、ズレたりして、隙間が生じてしまった場合は、谷樋の修理を行う必要があります。
谷樋の修理方法としては、屋根を剥がして、谷樋をすべて交換するのが最も確実です。
谷樋の修理の流れを紹介します。
✔屋根を剥がす
谷樋は、屋根材の下に設置されています。そのままの状態で、谷樋だけを外して交換することはできません。
工事の前に、まず、屋根を剥がす必要があります。
✔古い谷樋と防水シートを撤去する
屋根材を剥がしたら、古い谷樋を撤去します。雨漏りが発生している場合は、防水シート(ルーフィング)も劣化しているので、これも撤去しなければなりません。
下地の野地板も雨水を吸ってジメジメになっていて、劣化している場合は、撤去が必要です。
✔新しい防水シートと谷樋を施工し屋根材を葺く
下地材の上に新しい防水シート(ルーフィング)と谷樋を設置します。
その後で、外した屋根材をもとに戻します。
谷樋(谷板金)だけの修理が可能なのは瓦屋根のみ?
上記で紹介した谷樋(谷板金)だけの修理が可能なのは、瓦屋根の場合だけです。
現在、主流の屋根材となっている化粧スレートや金属屋根の場合は、谷樋の周囲の屋根材だけを外して工事することはできません。
剥がした屋根材を再利用することができないからです。
化粧スレートや金属屋根で谷樋の交換が必要な場合は、次の2つの方法のいずれかを選択することになります。
・屋根の葺き替え工事
・屋根カバー工法による工事
屋根の葺き替え工事とは、既存の屋根材や防水シート(ルーフィング)をすべて撤去して、新しい屋根材を葺く工事です。
屋根カバー工法による工事とは、既存の屋根の家に新しい屋根材を被せてしまう工事方法です。
屋根の葺き替え工事では、既存の屋根材等の撤去の工事や処分費用がかかりますが、屋根カバー工法ではその手間や費用を削減することができます。
ただ、屋根カバー工法を採用するには、屋根の下地がしっかりしていることが前提になります。
雨漏りの影響で屋根の下地が腐ったり傷んでいる場合は、下地の交換も必要になるので、屋根の葺き替え工事を行うしかありません。
谷樋(谷板金)を長持ちさせるためには?

谷樋(谷板金)は、屋根の中で最も雨漏りの原因になりやすい箇所です。谷樋がだめになってしまうと、屋根の全面的なリフォームが必要になってしまうことがあります。
谷樋を長持ちさせるためには素材選びからこだわりましょう。
✔ステンレスの谷樋を採用する
谷樋は、ステンレスのものもあります。ステンレスなら、ガルバリウム鋼板よりもさらに錆に強いので、穴が開いて、雨漏りしてしまうリスクが低くなります。
もちろん、海沿いなどではステンレスでも油断はできませんが、かなり長持ちすることは間違いありません。
✔勾配を高くする
谷樋の勾配が緩い場合は、雨水が流れにくく、谷樋が湿った状態になりやすいです。
この状態だと、錆も進行しやすくなり、谷樋の劣化が早まってしまいます。
これを防ぐには、雨水がスムーズに流れるように屋根の勾配を高くすることがポイントです。
既存の屋根の勾配が緩いために雨漏りにつながっている場合は、屋根の嵩上げ工事という方法もあります。
まとめ
屋根からの雨漏りは、様々な要因により生じますが、屋根と谷樋の取り合い部が雨漏りの原因として最も多いです。
屋根からの雨漏りが生じているときは、まず、この部分の劣化や異常を疑ってください。
Re,ルーフは、京都市右京区を中心に活躍する屋根工事職人直営店です。京都市や亀岡市などを中心に京都府全域で屋根工事や雨漏り修理工事を承っています。職人直営店なので、本当に工事に必要な費用だけで屋根工事や雨漏り修理工事を行うことができます。
屋根からの雨漏りでお困りの方は、早めにご相談ください。ご相談いただければすぐに対応いたします。